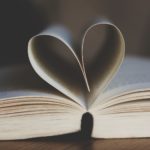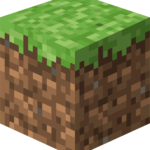芝生が枯れる原因の一つに「肥料焼け」があります。
「肥料焼け」とは、主に固形タイプの肥料が付着した芝の葉が枯れたり変色したりする症状のことですが、初めて芝生を張った人が犯しがちな失敗です。正しい知識がないまま肥料をまくと、芝生が肥料焼けを起こして枯れてしまうこともあるので要注意!芝生を育てるための肥料なのに逆にダメージを与えてしまうなんて悲し過ぎますし、ゼッタイ避けたいところですよね。
ということで、芝生が肥料焼けを起こさないための対策と手入れのコツをご紹介したいと思います。
❶夏場は液体肥料メインに
芝生の肥料焼けを起こさないためのコツ。
1つ目は「夏場の肥料やりは固形肥料は少な目にして易田肥料をメインで使っていく」という方法です。
夏場の炎天下で粒タイプの肥料を散布した後は肥料焼けを起こしやすいので、肥料焼けのリスクが小さい液体肥料を使う方が無難です。地域や芝生の状態・環境にもよりますが、最高気温が35℃をゆうに超えたりすると肥料焼けのリスクは非常に高くなるので、固形肥料の使用は慎重にならざるを得ません。液体肥料でも肥料焼けを起こすリスクはゼロではありません。ただ、固形肥料が芝の葉に付着したままの状態でカンカン照りの天気が続いた結果、肥料焼けを起こすというのがよくあるパターンです。なので、夏場は固形肥料をあまり使わず液体肥料をメインで使うということを検討してみましょう。もちろん、液体肥料を使うときは規定通りの希釈倍率で正しく使うことをお忘れなく!

何かと重宝する液体肥料
❷均一に肥料をまく
肥料焼けを防ぐ対策2つ目、それは肥料を均一にまく!ということ。
肥料を均一にまくのは基本中の基本ですが、これ実はとっても大事なことなんです。が、意外と均一に散布できていないことって結構あるんですよね・・・。たとえば、芝生全体が斜めになっていて撒いた肥料が水や雨で流されて結果的に「下流」の方に集まってしまうというパターン。いつも芝生の端っこの方の同じところばかり枯れたり、周りより低くなっている箇所が枯れたりするのであれば、これが原因かもしれません。同じ現象は芝生が凸凹していても起こり得ますね。凹んでいるところに肥料が集まってしまって肥料焼けを起こす・・・ということにも気を付けましょう。
また、固形肥料を手でつかんでバラまくと均一の散布にならず一か所に肥料が固まってしまい、結果的に肥料焼けを起こすこともあります。手作業ってやっぱり限界があるので上手に均一にまくのは実は難しいんです。慎重にまいていても手から固形肥料がドバっ!とこぼれ落ちることもありますし、散布できていないところが気になって後から追加で肥料をまいた時に大量にまいてしまったり。本人が気づいていないだけで、実は「一点集中!」とばかりに大量にまいていることは多々あります。
散布機を使うとより確実
対策としては「散布機」を使うことです。
家庭用の肥料散布機を選ぶ目安ですが、まず容量が10L程度あること。容量が少なすぎるととても使いづらいです。また、使用が楽な「手押し式」であること、高品質であること、そしてリーズナブルであること!これらをすべて満たしているのがコチラの肥料散布機。
|
|
安心のバロネスブランド!
均一に散布するのであればイチバン確実なのは散布機の利用です。うまく散布できる自信がない人は検討してみてください。
❸しっかり水やりをする!
3つ目の対策は、固形肥料をまいた後はしっかりと水やりをすることもお忘れなく!これは基本中の基本ですね。ただ、その基本がしっかりできていないことが結構多いんです。
たとえば、固形肥料をまいてホースで水やりをした後、芝生に顔を近づけてじっくり見てください。ついさっき散布した固形肥料、ちゃんと地表まで落ちていますか?芝の葉にひっかかっていませんか??
水やりが大事だと分かっていて水やりをしっかりしたとしても、肝心の肥料が地表に着地していないことってよくあります。ジョウロで水やりをサァーっとやったくらいでは固形肥料は芝の葉に引っかかって地表まで届かないので、ジョウロではなくホース等で勢いよく芝生にたたきつけるように散水する方が正解です。それくらいやらないと特に密度の高い芝生では芝の葉に引っかかったままになるので注意しましょう。
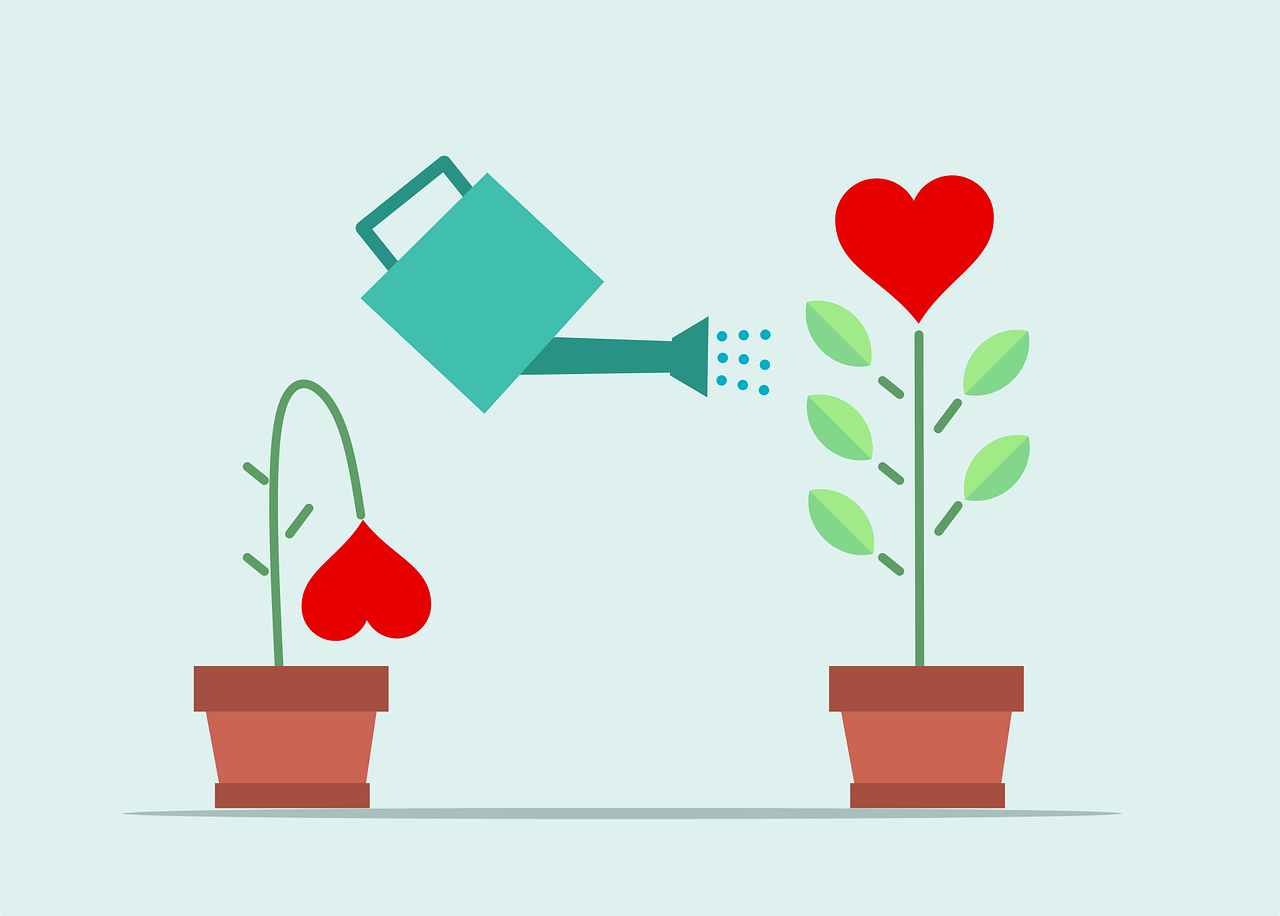
また、雨が降る直前に肥料を散布して水やりは雨に任せる、という方法もあります。ただ、その時も雨の量が少なかったり弱い雨だったりすると固形肥料は着地しません。意外と雨の勢いって強くないのでやっぱりホース等で勢いよく散水するのがベストなのです。なお、固形肥料をまいた後に水やりをしても、肥料がすぐに溶けて消えるわけではありません。散布後、数日間は消えずに残ったままになります。固形肥料を散布した直後の水やりはもちろん大事ですが、次の日やその次の日もしっかり水やりすることをおすすめします。
❹有機肥料を活用する
対策4つ目。肥料焼けを起こすリスクがより小さい「有機肥料を使う」こともおすすめします。
そもそも芝生が肥料焼けを起こす原因は「栄養濃度が高すぎる」ことにあります。よく使われている化成肥料は「窒素・リン・カリウム」がバランスよく含まれています。ただ、中には「高度化成肥料」として栄養分がかなりたくさん含有されている化成肥料もあります。たとえば「オール14」と言われるような「14-14-14」と表記されているような肥料がそれに当たりますが、そのような栄養たっぷり過ぎる化成肥料を与えると肥料焼けのリスクは高まってしまいます。一方、有機肥料は「窒素・リン・カリウム」の含有量は少なめで、栄養素をしっかり与えるのとはまた違ったアプローチで芝生を元気にする働きをします。化成肥料は「窒素・リン・カリウム」がバランスよく含まれていますが、化成肥料ばかりを使っていると土壌がどんどんやせ細っていくので、有機肥料も使いながら土壌を改良してくのがベストなんです。
参考記事:
おすすめの芝生の有機肥料
数ある有機肥料の中でも私が愛用しているのは「スーパーグリーンフード」。

20kg入りのスーパーグリーンフード
有機肥料にありがちな特有のニオイも抑えられているのでとても使いやすい肥料。芝生の育成・土壌改良・病害予防にもなりますのでとても重宝しています。
|
|
参考記事:
❺肥料の散布を控える
最後にご紹介する対策。それは・・・「肥料の散布を控える」という方法です。
「肥料焼け」って「肥料」が原因で起こるので、その「肥料」を与えなければ「肥料焼け」は起こしません。肥料焼けが怖いのであれば肥料を与えない!いわば究極の対策ですね。いやいやいや、肥料を与えなければ芝生は育たないんじゃないの!?って思う人もいるでしょうが、肥料をたっぷり与えなくても芝生は育ちます。もちろん、肥料がある方が栄養素のバランスは保たれますが、肥料を最小限にしても水やりと日光による光合成さえあれば芝生は育つんです。
たとえば、下の写真。
今年6月に芝張りをした我が家のTM9。芝張りをして2か月ということもありますが、そこそこキレイだと思います。色も濃く密度も高いですが、今のところ一切肥料は与えていません。水やりのみです。

肥料ゼロでも2か月でここまで育つ
芝張りをした初年度だから肥料を与えなくてもキレイなのかもしれません。来年、再来年は多少は肥料を与える予定です。ずーっと肥料ゼロでは厳しいとは思います。でも、これを見るだけでも何が何でも肥料が必須!!じゃないことはお分かりいただけるかと思います。
肥料よりも大事なこと
初心者にありがちなのは、芝張りをしてすぐにたくさんの肥料を与えて肥料焼けを起こすというパターン。早くきれいな緑の絨毯を見たいからと言って慌てて高濃度の肥料を与える人は結構おられますが、そんなことしなくても我が家の芝生のように肥料ゼロでもある程度は育ちます。「せっかく芝生を張ったのだからいろいろ手入れをしたい」という気持ちは分かりますし、ネットなどでは肥料をしっかり与えましょうと書いてあることは多いですよね。ただ、芝生をきれいにしたいのであれば肥料を一生懸命あげることよりも病気や害虫の被害から芝生を守る方がよほど大事!「肥料が足りなくて枯れる」よりも「病気や害虫で枯れる」ことの方が圧倒的に多いんです。
だから慌てて肥料をたっぷり与えるよりも病気予防で殺菌剤を散布したり、害虫予防で殺菌剤を散布する方が私は大事だと思っています。肥料をあげなければ・・・という呪縛にかかっている人はひょっとすると肥料メーカーさんの宣伝に踊らされている・・・だけかもしれませんね。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17d3d0d4.514f7af0.17d3d0d5.55c7141f/?me_id=1206626&item_id=10001681&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbaroness%2Fcabinet%2Fscotts%2F172466-9_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17d3d0d4.514f7af0.17d3d0d5.55c7141f/?me_id=1206626&item_id=10002912&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbaroness%2Fcabinet%2Fitem%2Fsgf-g-20-1-r_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)